令和8年4月1日から「住所・名前の変更登記」が義務化されます
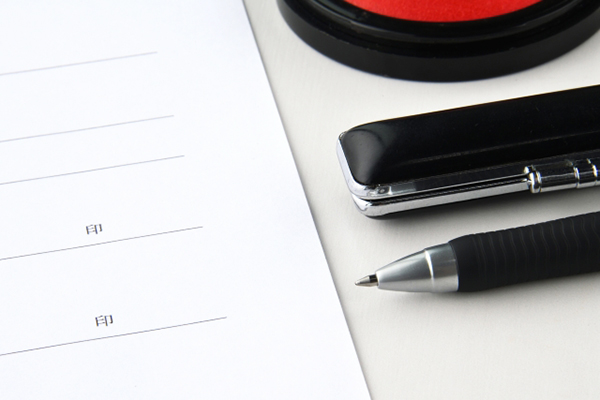
あさひ司法書士法人です。
令和8年(2026年)4月1日から、これまで任意だった「住所変更登記」「氏名変更登記」が義務化されます。
このブログでは変更登記の詳細についてお知らせします。
■変更から2年以内に
令和8年の4月1日から、住所や名前を変更した日から2年以内の「住所変更登記」「氏名変更登記」が義務化されます。
不動産の所有者が引っ越しされる場合や、婚姻・離婚などで住所や氏名が変わった場合は、変更から2年以内に登記申請をしなければなりません。怠ると過料が課される可能性もあります。
■義務化の背景
住所変更登記の義務化は「所有者不明土地問題」の深刻化がきっかけです。
登記簿上の住所が古いまま、もしくは登記されていない場合に所有者の確認をしやすくするために始まります。
国土交通省の調査では、所有者が特定できない土地は全国で約410万ヘクタールに上ります。その原因の約3分の1が「住所変更登記をしないまま放置していること」にあるとされています。
災害復旧や公共工事等の妨げにもなっており、国としても急務の課題となっているのです。
■2028年3月末までに対応を
今回対象となるのは、不動産を所有する個人・法人すべてです。
今後の変更だけではなく、過去に住所を変更して変更の登記をしないまま放置している場合も対象となります。
また、住所変更登記をしていないまま相続が発生すると、被相続人(亡くなった方)の住所変遷を証明するため、過去の住民票や戸籍附票の取得が必要です。
※その場合、複数の役所に問い合わせる必要が出ることがあります。
現在住所変更の登記をしていない状態にある方は、2028年3月末までの対応が必要です。十分にお気を付けください。
■あさひ司法書士法人へご相談を
「住所変更登記」「氏名変更登記」に関するご相談を承っております。
お気軽にお問い合わせください。
動画紹介
不動産所有者の方向けに法務省民事局より動画が公開されました。
ぜひご視聴下さい。
・不動産の所有者の方に必ず見てほしい動画です。住所・名前の変更の登記が義務化されます!(30 秒版)
https://www.youtube.com/watch?v=KiXkQQc33ik













